【灯油の消費実態】都道府県・市区町村別に見る灯油使用量と支出金額|青森が北海道より多い理由とは?
最終更新日:2025年5月
はじめに:なぜ地域で灯油使用量に大きな差が出るのか?
灯油は日本の多くの家庭で、冬季の暖房や給湯に用いられる重要なエネルギー源です。しかしながら、灯油の使用量や支出金額は都道府県や市区町村によって大きく異なります。本記事では、都道府県別・市区町村別の最新灯油消費データをもとに、地域ごとの特徴や、特に注目される青森県の高消費の理由を詳しく解説していきます。
灯油消費量・支出金額ランキング(2021年 総務省 家計調査より)
以下は、二人以上の世帯を対象とした年間の灯油使用量と支出額の都道府県別ランキングです。各都市の代表的な市でのデータになります。
| 順位 | 都道府県(都市) | 消費量(ℓ) | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 青森県(青森市) | 1,004.4 | 81,796 |
| 2位 | 北海道(札幌市) | 820.7 | 71,540 |
| 3位 | 岩手県(盛岡市) | 592.5 | 50,451 |
| 4位 | 秋田県(秋田市) | 585.5 | 49,069 |
| 5位 | 山形県(山形市) | 460.2 | 39,832 |
| 47位 | 兵庫県(神戸市) | 19.3 | 1,664 |
全国平均:消費量 152.6ℓ/支出金額 13,347円
なぜ青森県は北海道よりも灯油を多く使っているのか?
「北海道は日本で最も寒い」というイメージがありますが、灯油消費量では青森県が1位です。これは一見不思議に思えますが、以下の要因が関係しています。
1. 住宅の断熱性能の違い
北海道では古くから「高気密・高断熱住宅」が普及しており、室内の熱を逃さない工夫がされています。一方、青森県では必ずしも全世帯で断熱性が高い住宅が普及していないため、暖房効率が悪く、灯油の使用量が増加しやすいのです。
2. 都市ガス・集中暖房の普及度の違い
札幌市など北海道の都市部では、集中暖房や都市ガスなど、灯油以外の暖房手段が発達しています。一方、青森県は都市ガスの普及率が低く、灯油ボイラーやファンヒーターへの依存度が非常に高い状況です。
3. 通勤・通学時の暖房使用タイミング
北海道の家庭では日中外出中は暖房を切る習慣がありますが、青森県では在宅率が高く、日中も断続的に灯油暖房を使う家庭が多いとされています。
4. 車社会と灯油供給の環境
青森県は公共交通機関が少なく、自家用車中心の生活であり、定期的にホームタンクへ灯油を配送するインフラも発達しています。そのため、灯油の消費が自然に多くなる傾向があります。
灯油使用が多い地域の共通点と生活スタイル
- 寒冷な地域で冬の期間が長い
- 都市ガスや電気暖房の代替エネルギーが少ない
- 戸建住宅の割合が高く、部屋数も多い
- 24時間暖房など長時間稼働が一般的
地域別の家庭用エネルギーにおける灯油比率(環境省 2022年度)
| 地域 | 灯油のエネルギー構成比 |
|---|---|
| 北海道 | 51.6% |
| 東北地方 | 40.7% |
| 関東甲信 | 8.7% |
| 近畿地方 | 4.5% |
| 沖縄県 | 5.6% |
灯油は特に北海道・東北で高い比率を占めており、家庭のエネルギー源として重要な役割を果たしています。
市区町村別データの取得方法と注意点
市区町村単位の詳細な灯油消費データは、国レベルでは一般に公開されていません。ただし、一部自治体では独自にエネルギー白書や温暖化対策計画の中で、家庭用エネルギー使用状況を発表しています。
例:
灯油価格と消費者負担の今後
2022年以降、原油価格や為替変動、国際情勢の影響により、灯油価格は上昇傾向にあります。寒冷地に住む世帯ほどこの影響を強く受けるため、節約術や他熱源への転換が課題となっています。
まとめ:地域に応じた灯油対策が今後ますます重要に
青森県が全国一の灯油消費量を誇る背景には、住宅性能、暖房習慣、都市ガスインフラの未整備など、複合的な要因が存在します。
灯油に依存する生活スタイルを今後も続けるためには、価格変動への備えとエネルギー効率の改善が必要不可欠です。

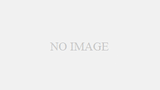
コメント