【災害対策】非常時にこそ頼れる!プロパンガスの強靭な供給体制と防災活用法
災害時、ライフラインで最も復旧が早いのは「LPガス」
地震や台風などの大規模災害が発生すると、ライフライン(電気・水道・ガス)は広範囲で停止します。その中でも、最も早く復旧できるエネルギー源がLPガス(プロパンガス)であることは、あまり知られていません。
実際、2011年の東日本大震災や2016年の熊本地震では、LPガスは災害直後から一部地域で稼働可能となり、復旧速度・柔軟性において高く評価されました。
なぜLPガスは災害に強いのか?その3つの理由
- ① 各家庭に独立供給されている
都市ガスのように一括供給ではなく、戸別にボンベ供給されているため、一部地域のインフラ被害でも影響が限定的。 - ② 復旧作業が迅速
ガス会社の配送車がタンクを入れ替えるだけで供給再開が可能。大規模な管路修復が不要。 - ③ 備蓄性が高い
家庭ごとのボンベ内に2週間〜1ヶ月分の燃料が常時備蓄されているため、非常時のエネルギーとして活用可能。
災害時に役立つLPガス機器と使い方
- カセットコンロ・LPガスボンベ式コンロ:停電時も調理可能。屋外・換気に注意。
- ガスファンヒーター:電源不要タイプもあり、寒冷地の避難所で重宝。
- ガス給湯器:停電に対応したモデルであれば、温水供給が継続可能。
- ガス発電機:一部地域では、LPガスを燃料とした自家発電機が導入されている。
特に直結型のLPガス器具は、停電時の「命を守る装置」としても期待されています。
自治体でも進む「災害対応型LPガス」の導入
全国の自治体では、避難所・防災拠点において「防災対応型LPガス設備」の導入が進んでいます。
- ・仮設住宅へのボンベ供給
- ・炊き出し用コンロの設置
- ・緊急時電源用ガス発電機
例えば、岐阜県や高知県では「非常用LPガス供給システム」を地域一帯に整備し、住民のエネルギー確保を平時から準備しています。
家庭でできるLPガス防災対策5選
- ① ガス器具の使用方法を家族で共有
- ② 停電時にも使える器具を準備(カセットコンロなど)
- ③ ガスボンベの位置や締め方を把握
- ④ LPガス事業者と緊急時連絡先を明記
- ⑤ 年1回のガス機器点検で安全を維持
特に小さなお子さんや高齢者がいる家庭では、平時の訓練と情報共有が災害時の安心につながります。
まとめ|LPガスは「もしも」の時に力を発揮するエネルギー
災害時にこそ、LPガスの独立性・復旧性・備蓄性は非常に頼れる特性です。家庭でも、災害に備えてガス機器や連絡体制を整えておくことが重要です。
「防災=備え」の時代。日常で使うLPガスこそが、非常時の“命綱”となる可能性を、今一度見直してみてはいかがでしょうか。

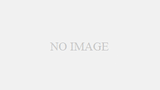
コメント