【びわとびわもどきの違い】見分け方・味・育て方まで徹底比較!
「びわ」と「びわもどき」って何が違うの?
「びわ」と「びわもどき」は、その見た目がとても似ていることから、混同されがちな果実です。しかし、実際には植物の分類、味、用途、育て方に至るまで多くの違いがあります。本記事では、それぞれの特徴と違いを徹底的に解説していきます。
「びわ」とは?基本情報と特徴
「びわ(枇杷)」は、バラ科ビワ属の常緑高木で、日本では古くから親しまれてきた果物です。
- 学名:Eriobotrya japonica
- 原産地:中国南部
- 果実の色:オレンジ~黄橙色
- 味:ジューシーで甘く、やや酸味あり
- 用途:生食、びわ酒、ジャム、ゼリー
実は初夏に熟し、房状にたくさん実ります。果肉はやわらかく、皮をむいてそのまま食べるのが一般的。ビタミンAやポリフェノールも豊富で、健康果実としても知られています。
「びわもどき」とは?正体と特徴
「びわもどき」とは、一般的にナンヨウビワ(南洋枇杷)やムクロジ科のクロウメモドキ属などの似た外見を持つ植物を指します。名前の通り、「びわに似ているが別物」という意味で、複数の植物が該当します。
代表的な「びわもどき」:
- クロウメモドキ属の果実(食用不可)
- ナンヨウビワ(食用には向かない)
- 観賞用に育てられる外見が似た園芸品種
多くの場合、果実は食べられないか、味が劣るため観賞用とされています。
びわとびわもどきの違いを比較表でチェック!
| 項目 | びわ | びわもどき |
|---|---|---|
| 分類 | バラ科ビワ属 | ムクロジ科など(属は多様) |
| 果実の色 | オレンジ〜黄橙 | 黒っぽい・赤紫・緑系など |
| 味 | 甘くてジューシー | 苦味・渋みあり(多くは不味) |
| 食用 | 可 | 基本的に不可 |
| 開花時期 | 冬(11月〜1月) | 品種による |
| 収穫時期 | 初夏(5〜6月) | 種によって不定 |
| 用途 | 食用・加工・薬用 | 観賞用・野生種 |
なぜ「びわもどき」と呼ばれるのか?
「びわもどき」という名前は、実や葉の形が「びわ」に似ていることから名づけられました。ただし、見た目は似ていても、植物学的にはまったく異なる種類であり、混同して食べるのは危険なケースもあります。
特に野生のクロウメモドキ属の一部は毒性を持つ場合もあるため、野生の果実を「びわ」と勘違いして食べないよう注意が必要です。
びわの栽培方法と育て方
びわは比較的育てやすい果樹で、家庭でも楽しめます。
育て方のポイント:
- 植え付け時期:秋または春
- 日当たり:よく日の当たる場所
- 水やり:土が乾いたらたっぷり
- 剪定:毎年冬に樹形を整える
- 収穫:5〜6月に色づいた果実を摘む
鉢植えでも可能で、2〜3年で結実する場合もあります。
「びわもどき」は栽培する価値がある?
びわもどきの多くは観賞用とされており、特に実の観賞や葉の形状を楽しむために育てられています。果実目的では育てられないため、家庭菜園としてはあまりおすすめされません。
ただし、ナンヨウビワなど一部は南国の景観樹として人気があります。
よくある質問(FAQ)
- Q. 野生のびわもどきは食べられますか?
- A. ほとんどは食用に適さず、苦味や毒性を持つ場合もあるため注意が必要です。
- Q. 家庭で育てるならどちらがおすすめ?
- A. 果実を楽しみたいなら「びわ」がおすすめ。観葉植物や景観重視なら「びわもどき」も選択肢です。
- Q. スーパーで売っているのはどっち?
- A. 基本的にスーパーで販売されているのは「びわ(Eriobotrya japonica)」です。

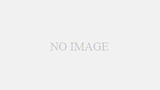
コメント